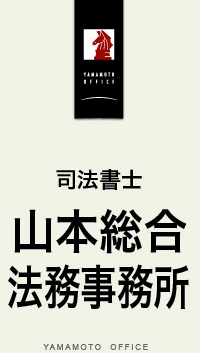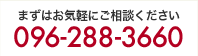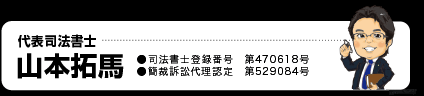TOP > スタッフブログ

2014年8月アーカイブ
最近のお墓事情
こんにちは、FPの山本洋子です。
我が家では、お盆には必ず夫婦それぞれの実家の墓参りをしますが、どちらも祭祀承継者ではないので、そろそろ自分たちのお墓のことを考えなければならないと思っています。
これまでお墓といえば、家墓(いえはか)に代々入るというイメージだったのが、近年、さまざまな理由から、自分らしいお墓に入りたいという方が増えているようです。
実際、 私の夫も、ある自然葬の墓地見学に参加し、自分の目や耳で確かめています。以前は、生まれ育った故郷の海に散骨してほしいとも言っていたので、結論を出すにはまだまだ情報収集が必要だと思っています。
最近、新聞やテレビでも話題に上る機会が増えているので、ご存知の方も多いと思いますが、大まかに供養のスタイルを分けてみました。
どれを選ぶかは、お墓を継承してくれる人がいるかどうかが分かれ目になります。
・承継者がいる・・・・・・・・・・・先祖代々の墓、新規の墓
・承継者がいない・・・・・・・・・納骨堂、永代供養墓、合葬墓、樹木葬、散骨など
承継者はいるけれども、不便などの理由で、お墓の改葬(古い墓地から新しい墓地への引っ越し)を希望されるなら、次のように、墓埋法(墓地、埋葬等に関する法律)に基づいた手続きが必要になります。
① 新しい墓地の受け入れ証明書を発行してもらう
② 古い墓地を管理運営しているところで、埋蔵証明書を発行してもらう
③ 古い墓地の自治体で、改葬許可証を発行してもらう
④ 遺骨の取り出し、閉眼供養をする
⑤ 更地にして変換する
⑥ 新しい墓地に、改葬許可証を提出する
⑦ 納骨、開眼供養をする
しかし、承継者がいても、お墓の継承を強制したくないなどの理由から、永代供養墓や樹木葬、散骨などの自然葬への関心が高まっているのも事実です。
いずれにしても、周辺の環境、交通の便、設備、管理態勢、費用、供養の方法など、メリットとデメリットを事前に十分確認し、価値観に見合うものであるかどうかを見極めることが大事だと思います。
また、死後の対応をしてくれる人と、考え方に食い違いが生じて親族間でトラブルにならないよう、遺言の中で意思表示をしておくことも大事かと思います。
少子高齢化が進む中で、お墓のスタイルが変化していくのも自然な成り行きかもしれませんね。