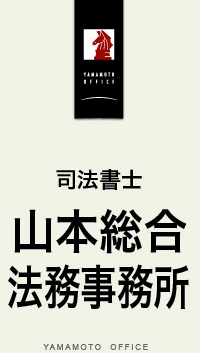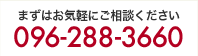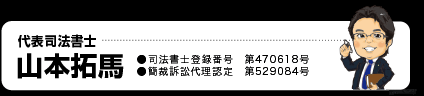TOP > ご相談事例
成年後見アーカイブ
任意後見制度とは、どのような制度ですか?
任意後見制度は、本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を、公正証書によって結んでおくものです。
本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
法定後見制度と違って、自ら希望する人物を代理人とすることができるため、より安心して財産の管理などを任せることができます。
成年後見人等の任期はいつまでですか?
通常、本人が病気などから回復して判断能力を取り戻すか、亡くなるまで、成年後見人等としての責任を負います。
また、成年後見人等を辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となり、正当な事由がある場合に限られています。
成年後見人等でもできないことはありますか?
一身専属的なこと(遺言など)はできません。
その他には、身分行為(婚姻、離婚、養子縁組など)や医療行為の同意(手術など)、本人の債務の保証人になることや身柄を引き取ること(身元保証人となること)などもできません。
成年後見人等の役割は何ですか?
成年後見人等の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。
成年後見人等の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の仕事ではありません。
また、成年後見人等はその事務について、家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
成年後見人等には、どのような人が選ばれるのですか?
家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選任します。本人が必要とする支援の内容によっては、申立ての際に挙げられた候補者以外の方(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家)が選任されることもあります。
法定後見制度を利用するためには、どうすればいいのですか?
法定後見は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることで利用できます。
申立てができる人は、本人・配偶者・四親等以内の親族などに限られていますが、申立てる人が誰もいない場合などは、市町村長が申立てます。誰を成年後見人や保佐人・補助人とするかは、候補者を申し出ることができますが、最終的には家庭裁判所が適任かどうかを判断して決めます。
法定後見制度の「後見」「保佐」「補助」はどのような違いがあるのですか?
■「後見」に該当するのは、判断能力がほとんどない方です。
成年後見人の権限として、財産管理についての全般的な代理権、取消権が与えられます。
また、成年被後見人(本人)には、医師・税理士等の資格や会社役員・公務員などの地位を失う、印鑑登録ができなくなる、選挙権を失うなどの制限があります。
■「保佐」に該当するのは、判断能力が著しく不十分の方です。
保佐人の権限として、特定の事項について、同意や取消しができます。また、本人が同意した事柄についての代理行為を行うことができます。被保佐人(本人)には、医師・税理士等の資格や会社役員・公務員などの地位を失うなどの制限があります。
■「補助」に該当するのは、判断能力が不十分な方です。
補助人の権限として、本人が同意した事柄について、同意や取消し、代理行為を行うことができます。「後見」や「保佐」のような資格に関する制限はありません。また、申立には本人の同意が必要です。
成年後見制度には、どのような種類があるのですか?
■任意後見制度(判断能力が不十分になる前から)
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。
■法定後見制度(判断能力が不十分になってから)
既に判断能力が不十分になっている場合に、家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選んでもらう制度です。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。本人の判断能力に応じて「後見」「補佐」「補助」の3つの制度が利用できます。
成年後見制度とは、どのようなものですか?
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、それらの方を法律的に支援する制度です。