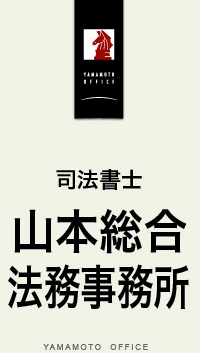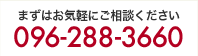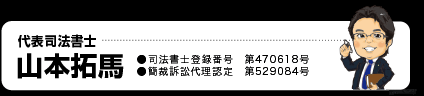TOP > ご相談事例
相続・遺言のことアーカイブ
夫から相続した住宅のローンを払えないのですが、何か方法はありますか?
まだ住宅ローンの返済が終わっていない住宅を相続された場合、原則として「相続放棄」などの手続きをとらない限り、亡くなったご主人の住宅ローンの返済義務も相続しなければなりません。
つまり、今回あなたが相続した場合は、ご主人に代わって住宅ローンの返済をしていかなければなりません。
ただ、通常は住宅ローンの契約時に団体信用生命保険に加入するのが一般的です。この保険に加入していれば、住宅ローンの返済中にご主人が死亡しても、保険会社が残ったローンを融資先の金融機関に支払い、住宅ローンは全て支払われます。
まずは、この保険の加入状況を確認する必要がありますが、場合によっては相続放棄や債務整理などの手続きを検討する必要もあるでしょう。
相続放棄の場合は、利用できる期限がありますので、早めに相談されることをお勧めします。
父が借金していましたが、借金も相続されるのでしょうか?
借金というマイナスの財産も相続の対象となるため、相続されます。
しかし、相続人となったことを知ってから3か月以内に相続放棄をすれば、借金を相続しなくてすみます。ただこの場合には、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も全て放棄することになりますので、ご注意下さい。
3か月という短い期間ですので、早期の段階で相談されることをお勧めします。
相続人の中に、行方不明者がいます。このままでは、遺産分割協議を進めることはできないのでしょうか?
このままでは遺産分割協議を進めることはできませんが、
次のような制度を利用することで進めることができます。
まず、行方不明の方のための財産管理人(不在者財産管理人)を選任することができます。行方不明の方にかわって、不在者財産管理人が協議に参加することで、手続きを進めることができるのです。
また、行方不明者の生死不明の状態が7年以上続いていると、失踪宣告という手続きで、その行方不明者を死亡したものとして、残りの相続人で遺産分割協議を進める方法もあります。この手続きも裁判所に書類を提出して行いますので、司法書士にご相談いただくと安心です。
遺産分割協議でもめています。話を進める方法はありますか?
遺産分割にあたり、親族間での話し合いがまとまらない場合は、裁判所で行う調停手続きを利用することを検討してみるのも良いと思います。
第三者である裁判所や調停委員がいる中で、法律にのっとって話を進めることができ、早期解決にもつながります。
調停申立書などの裁判所へ提出する書類は、司法書士が作成できますので、安心して調停手続きを利用できます。
遺産分割協議とは、何をするのですか?
遺産分割協議とは、相続人全員が集まって遺産をどのようにして具体的に分けるかについて話し合うことを言います。相続人が一人でも欠けていれば遺産分割協議は成立しません。
遺産分割協議をする前に確認あるいは注意しておかなければならないことは、
①協議に参加すべき相続人が、もれなく全員参加しているかどうか?
②遺産が間違いなく故人の財産であり、他に見落とした遺産はないか?
③故人の生前中に、結婚資金や独立資金を受けていた相続人はいないかどうか、
その結果、相続分について争いはないかどうか?
・・・といった点です。
これらの問題をきちんと整理してから遺産分割協議を始めなければ、協議そのものがまとまらず、親族間の紛争にまで発展する可能性もあるので注意が必要です。
遺言書を作成したけど、気持ちが変わった場合に内容を変更できますか?
気持ちが変わった場合は、内容を変更できます。
「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と、民法1022条で規定されています。
つまり、前に作成した遺言書の一部または全部を撤回するという遺言書を新たに作成することで、遺言書の内容を変更することができます。
遺言書を作るタイミングは、いつが良いのでしょうか?
法律上は、15歳に達している方はいつでもできますので、思い立った時が一番良いタイミングではないかと思います。ただ、何か大きな出来事がないと踏み出せないものでしょうから、例えば、次のようなタイミングが考えられます。
配偶者や親兄弟が亡くなった時や、引退・退職後の人生プランを考える節目として作成したり、結婚記念日に「全ての財産を妻に相続させる」という内容の遺言書を作成したい、という方もいらっしゃいます。
遺言書に書いた内容は、確実に実現されるのでしょうか?
確実に実現されるためには、遺言の中で、遺言執行者を選任しておくことをお勧めします。
遺言の内容を実現(執行)する人のことを遺言執行者といい、遺言の中で指定することができます。そして、遺言執行者を定めた場合、遺言の内容に不満のある相続人が、遺言の内容に反するような勝手な行動をしても無効となるため、遺言執行者を選任しておくことで安心できると思います。
また、遺言執行者には誰を指定しても良いのですが、遺産に不動産が含まれている場合には、不動産の名義変更の専門家である司法書士を遺言執行者に選任しておけば、より迅速に名義変更ができるため、安心です。
遺言の方法はいくつかあるそうですが、どの方法が良いのでしょうか?
自筆証書遺言か公正証書遺言を利用する方法が一般的ですが、公正証書遺言をお勧めします。
自筆証書遺言は様式不備で無効になったり、紛失や偽造変造などの心配が否定できません。
また、遺言書の開封時には家庭裁判所での検認手続きを経る必要もあります。
一方、公正証書遺言は、公証役場で保管されるため紛失の心配もなく、他の人に手を加えられる心配もありません。家庭裁判所での検認手続きも不要であり、遺言者が亡くなった後すぐに遺言の内容を実行できます。
必要書類の収集や公証人との打ち合わせについても、司法書士などの専門家に代行してもらえば、遺言する方はほとんど手間をかけずに遺言書を作成できます。
他にも遺言書を残しておかないと困ることはありますか?
遺言書を残しておかないと困る可能性が高いと予想されるのは、
次のような人たちです。
● 子供がいない夫婦
● 複数の子供がいるなど、相続人がたくさんいる人
● 独身で身寄りがない人
● 再婚した人
● 内縁の妻(夫)や婚外子がいる人
● 介護が必要な家族がいる人
● 行方不明の家族がいる人
● 遺産の大半が、自宅の土地・建物だけという人
● 会社や個人事業の経営者
このようなケースに該当する人は、ぜひ、遺言書の作成を検討されることをお勧めします。